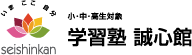こんばんは、上熊須です。
今回は志望校の選び方と、その後の勉強について話したいと思います。
中3、高3の人はもう志望校を決めていないといけない時期ですね。
中2、高2の人もそろそろ選び始めてもいいころです。
志望校を選ぶときにどうしてもここに行きたいというものがある人も、そうでない人も志望校選びは今後を決める重要な事柄です。
そこで2つのパターンに分けて志望校選びのコツを教えたいと思います。
1つ目は行きたいところが特に決まってない人です。
現在の学力の1ランク上を志望校にして、そこを目指して勉強しましょう。
しっかり勉強して成績が上がればそのまま受け、成績が上がらなくても志望校を1ランク落として元の学力通りの志望校に行くことができます。
ここで大切なのは、成績が不十分であれば無理に上の学校を受けないことです。
志望校を最初に決める段階では上を見て、入試直前では足元を見ることが自分の実力にあった学校に入るコツです。自分も京大から阪大に落として無難に合格しました。
2つ目は行きたいところが決まっている人です。
よっぽど成績が足りないとかでなければ、行きたい学校を志望した方がいいです。
大学に入学してからのモチベーションが変わります。大学入学はゴールではありません。
しかし、逆に行きたい大学を逃したらほかに行ける場所が無いことが多いです。学校のレベルでは足りません。もう1段上の成績をとれるまで安心はできません。
成績に余裕がなければほかの学校も受けられるような科目選択を行いましょう。
どちらの場合でも、目標を高めに立てるのはいいことですが、それ以上に試験直前にきちんと自分の学力を認識することが大切です。またそれだけでなく、志望校を下げることに家族、先生が反対しない事も大切です。
これはあくまで極論ですが、自分の学力で受かる学校を志望すれば入試は受かります。逆に受からない学校に志望したら受かりません。
入試の合否は志望校の選び方によって決まるといっても過言ではありません。
願書を出す際は自分の力を過信しないようにしましょう。