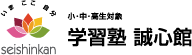こんにちは、講師の今井です。日に日に寒くなって家からどころか布団から出るのが難しくなってきましたね。さらに寒さだけでなくインフルエンザも流行ってきました。受験生の方は特に健康に気をつけて下さい。
今回は、担当生徒を見て感じた事について書いていこうと思います。うちの塾では毎回塾長が担当生徒と席の位置を決めています。
その中には初めてみる生徒もいますが、多くは毎週同じ生徒がほとんどです。同じ生徒を毎週見ていると、だんだん生徒の特長というものが見えてきます。
この生徒は文章題が苦手であるとか、長文を読むのに時間がかかるだとか本人にもわかりやすいものから、問題に対する考え方や、覚え方など本人ではあまり意識できないものもあります。
前者に関しては、正直出来るようになるまでやるしかないと思います。
そのためより重要な物は後者の方が重要なのではないかと思います。答えを見るときにそれがわかると思います。各問題に対する考え方がしっかりしている人は答えを見る時に解く手順だけではなく、なぜそんな解き方をするのかについても理解しようとしています。
そのため、煮た問題をしばらくしてから解いても、解き方を理解しているため自力で解くことが出来ます。一方、答えを見る時にこうやって解くのかと“覚える”というより思うだけで終わっている気がします。そのため、すぐに似た問題を解いても解き方が頭から出てこずに、答えを見て「ああ、そうだった」という反応をします。
私は、勉強において覚えるというより理解することが重要だと思います。学力が記憶力だけではないのはこの理解するということも必要だからです。理解していれば、応用問題が来ても対処する武器が頭から自然と出てくると思います。
よく効率よく勉強するにはどうすればいいかという質問がありますが、”理解する”ことは時間がかかるため、効率がいいとは言えません。
しかし、理解するということは対応力を身につけるということでもあります。
そのため受験という長い目で見れば効率的であるといえると思います。勉強するときは“答え”に対する考え方を工夫してみてください。